トピックス
ロジカルシンキングはもう古い? 情報濁流時代を勝ち抜く「本質をつかむ力」とは
目次(Table of Contents)
情報が氾濫する現代社会で、本当に大切なものを見極めるにはどうすればいいのか? 2025年5月に発売された『本質をつかむ』(フォレスト出版)の著者・羽田康祐さんに、今こそ求められる「本質をつかむ力」についてインタビューしました。なぜこの力が不可欠なのか、ロジカルシンキングとの違い、そして誰もがこの力を育む方法を深掘りします。羽田さんの仕事哲学や、会社ASAKOへの深い想いにも迫ります。
プロフィール:羽田康祐(はだ こうすけ)
大学卒業後、ベンチャー・中堅広告代理店を経て、ASAKOへ。その後、外資系コンサルティング企業での経験も経てASAKOに戻り、現在に至る。ASAKO社員歴は累計20年のベテラン。
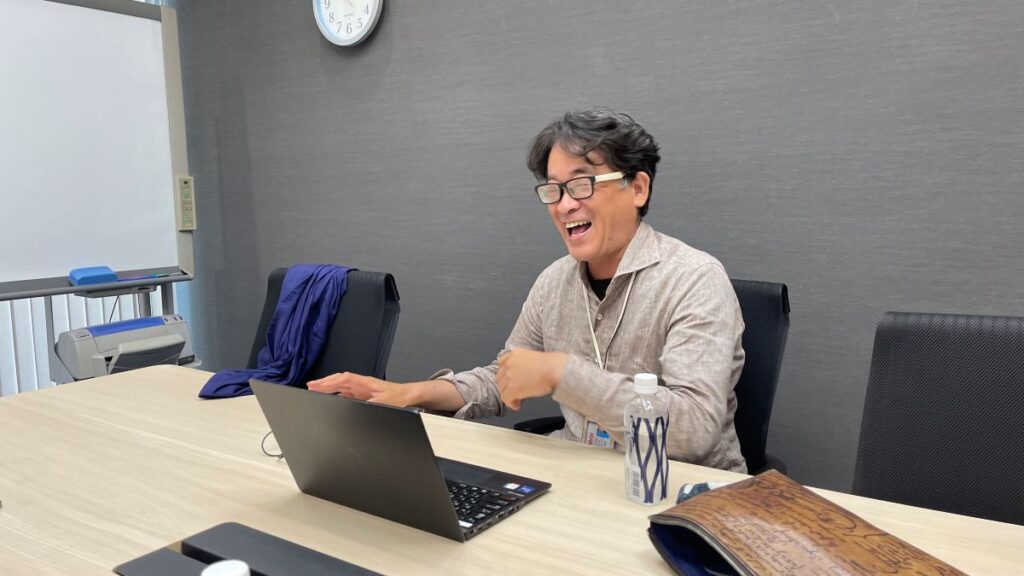
(羽田さん写真)
息子さん一人と双子の娘さん2人、そして奥様との5人家族。セキセイインコの「ムギ」とウロコインコの「マッチャ」と戯れるのが、至福の時間。「インコって、実は飛ぶよりも歩くことの方が多いんですよ。ズボンをよじ登ってくる姿がかわいくて」と、笑顔で語ってくれました。
1 なぜ今「本質をつかむ力」が求められるのか
これまでの著書で数々のテーマを世に送り出してきた羽田さんが、なぜ今、「本質」にフォーカスした一冊を書こうと思ったのか。情報があふれる現代社会におけるその必要性を深掘りします。
「本質を見抜く力」というテーマは、いつか本にまとめたいと思っていました。私が社会人になった1990年代からインターネットが普及し始め、今ではいつでもどこでも膨大な情報にアクセスできます。最近では生成AIも登場し、私たちの生活はより一層便利になりました。しかし、世の中にあふれる情報は玉石混交です。何が正しく、何が誤っているのか、見極めるのがますます難しくなっています。だからこそ今、「本質をつかむ力」が重要なんです。
──情報濁流時代に、どのような危機感を抱いていますか?
情報過多の時代に抱く危機感は、大きく2つあります。
1つ目は、「状況反射的」に仕事をする人が増えていることです。たとえばマーケティングの現場は、コンバージョンなどの数値に左右されがちです。ある広告施策で資料請求が増えれば、同じ広告を増やす。逆に効果がなければ、別の広告に変える。そんな風に、背景や原因を深く考えず、状況反射的な対応をする。つまり、本質を見失いやすい環境になってしまいました。
──最近は「タイパ」や「コスパ」という言葉もよく聞きますね。
まさに、それにも通じるところがあります。タイパやコスパの考え方は、いかに効率よくゴールできるかを重視します。そこで私が感じている2つ目の危機感が、「寄り道」をしなくなったことです。KPIなどの短期的な指標に向かって効率的な道を選ぶようになり、偶然の出会いや発見がなくなりました。その結果、皆が似たような考え方に陥り、異なる視点や新しい提案が出てこなくなったんです。
──それが、今回の著書でも触れられている「可視化依存社会」ですね。
はい。今の社会は、何でも「可視化」される傾向にあります。コンバージョンやKPIなど目に見える情報に踊らされ、その背景を深く考えようとする人が少なくなりました。もちろん、20年前の時点で状況反射的に動くような仕事の進め方はゼロではありませんでした。しかし、それでも少し立ち止まって考える余裕はありました。今はその余裕すらなくなり、仕事の質にも影響していると感じます。
2 そもそも「本質」とはなにか?
目に見える情報にあふれる今の時代において、「本質をつかむ」とはどういうことなのでしょうか。そしてそれは、これまで注目されてきた「ロジカルシンキング」とどう違うのか。その考え方や実践例を聞きました。
本質とは、簡単に言うと、目に見えない「核心の部分」です。私は、物事は、重要なものほど目に見えないと考えています。たとえば、お金や土地といった資産は後からでも手に入れることができます。一方で、カルチャーやリーダーシップのように目に見えないものは、一度失われたら簡単には取り戻せません。本質をつかむには、表面的な情報ではなく、「なぜそうなったのか」といった背景を問い続けなくてはいけない。そうすることで、真の意味や価値を見出すことができるんです。
──似たような思考スキルとして、ロジカルシンキングがありますよね。
そうですね。かつては「ロジカルシンキング」が注目され、私も『推論の技術』(フォレスト出版)という本でそのテーマを扱いました。ただ、この2つは大きく異なります。ロジカルシンキングは、矛盾なく物事を説明する力として非常に有効です。ただし、目に見えるものを積み上げていけば、誰でも同じ結論にたどり着きます。つまり、そこで生まれるアウトプットには差がつきにくく、付加価値も生まれません。
一方、「本質」は、目に見えないため、ほとんどの人が気づいていません。つまり、本質を見抜くこと自体に価値があり、イノベーションを起こす力になるのです。市場が成熟して売上や利益が伸び悩んでいる企業が多い中、物事の重要な核心を捉え、大きく変えていくような力が必要とされています。
──実際の仕事の中でも、「本質をつかむ力」が求められる場面はあるのでしょうか?
はい、あります。たとえば「社名とロゴを変えたい」という話があったとします。この場合、よくあるのは、「過去に社名を変更した事例はこうです」「こんなに美しいロゴを作れます」とクライアントに提案する方法でしょう。でも私は、「なぜ社名やロゴを変えたいのか?」と問うところから始めます。
もしかしたら、「今の社名が古臭く、変えることで若手の採用競争力を高めたい」という理由があるのかもしれません。問い続けていけば、社名を変えることが本当に採用力向上につながるのか? 他にもっと効果的な手段はないのか? と考え直す必要が出てきます。このように、本当のニーズを探るのに、本質を見抜く力が欠かせないんです。
──そのためには、どうすればいいのでしょうか。
大切なのは「対話すること」です。過去の事例を提示するのは、そのあとで十分。まずは表面的なニーズに飛びつかず、その背景にある「なぜ?」をじっくり聞き出します。これは、クライアント担当者やマーケターだけでなく、これから社会に出ていく学生の皆さんにも伝えたいことです。目に見える情報や結果だけを鵜呑みにせず、「その裏にある本当の目的は何か?」を常に疑いながら考える。そうした姿勢が、結果的に付加価値につながり、成果に結びつくのだと思います。

(羽田さん写真)
「ASAKOの社員も、すぐに事例を探そうとしがちです。でもそれでは本質にたどり着けない。この本を読んで考えるきっかけにしてほしいのですが、“読んでね”って言うと印税目的っぽくて言いづらくて(笑)」
3 長期で築く本質的な競争力
1年で得た競争力は、1年で模倣される。そんな短期的な成果に振り回される時代だからこそ、「5年、10年かけて築いた競争力こそが本物」だと語る羽田さん。このような、長期的な視点は、日々変化する広告の現場においても欠かせないといいます。では、広告における“本質”とは何か。羽田さんの考えを聞きました。
──広告業界にも、長期的な視点は必要なのでしょうか?
もちろん必要です。デジタル広告の世界では、ページビューやCTR(クリック率)、コンバージョンといった指標を毎日追いかけ、その結果をもとに広告の差し替えを繰り返すのが一般的です。それも重要ではありますが、広告の本質的な目的はそこではありません。本当に大切なのは「広告を出さなくても買ってもらえる状態」をつくることです。そのためには、感情移入されるようなブランドをつくる必要があります。私は、広告とはそうしたブランドづくりのためにあると考えています。
例としてよく挙げるのが、ハーゲンダッツです。「贅沢なアイスクリームを食べたい」と思ったとき、多くの人は自然とハーゲンダッツを思い浮かべるはずです。それは、長年かけて「スーパープレミアムアイスクリーム」というブランドポジションを築いてきた結果です。そうなれば、デジタル広告の運用で疲弊することもなくなるはずです。
──羽田さんが目指す広告像が、少し見えてきました。
私たちが目指す広告は、多くの人にとって「第一想起」になることです。つまり、「こういう商品があるんだ」という出会いの瞬間をつくること。そして、その出会いをきっかけに、そのブランドを手にしたことで自分の人生が1ミリでも良い方向に変わる。振り返ったときに「出会ってよかった」と思ってもらえるような体験を届けたいのです。広告とは、そうした出会いの入り口をつくることができます。「この商品があってよかった」「このブランドに出会えてよかった」と思う人が増えていくこと。企業も消費者も社会にとってウィンウィンが広がっていく。それが一番理想的で、長く愛される強いブランドを築くのが、私たちが考える広告です。
4 羽田さんが仕事で大切にしている本質とは
なぜ、これほどまでに「本質」を追い求め続けてこられたのか。その疑問を投げかけると、羽田さんの根底にある価値観、そしてASAKOという会社への深い想いが見えてきました。
実は、コンプレックスがあったんです。新卒で入社したのは広告業界のベンチャー企業。一方、同期たちは大手の広告会社に就職し、大きな案件を任されている。そこで、広告やマーケティングの知識だけは誰にも負けないように、「知識」を身につけようとしました。20代は貯金もほとんどせず、給料のほぼすべてを本に費やしていました。最終的に買った本は1000冊以上。水道を止められたこともありましたし、結婚する時は貯金がなくて結納金すら払えませんでした。でも、その知識の積み重ねが、「本質をつかむ力」を育ててくれました。
──その力が、現在の仕事にも活きているのですね。
はい。ただし、本質が見えているからといって、すぐに評価されるわけではありません。自分ひとりだけが気づいていても、周囲に共有・共感されなければ組織は動きません。「本質」が目に見えないものである以上、言語化して伝えるのも難しく、社内の空気に押されて「もういいか」と諦めそうになることもあります。
皆さんの会社でも、本質から外れているにも関わらず、「量や数を追う」ことが優先され、本当に必要な「質」の部分が見過ごされている場面があるのではないでしょうか。どれだけ量や数を追いかけても、その一つ一つに競争力がなければ、成果につながりません。しかし「競争力」や「質」は、目に見えないものなので、なかなか理解されにくい。結果として、本質に気づいている人ほど「量」や「数」に対して疲弊していく。そういう悪循環に心当たりのある方もいるのではないでしょうか。
──ちなみにASAKOの社内カルチャーはどうなのでしょうか?
ASAKOは、昔から良い人が多い会社だと感じています。誠実で努力家な人が多く、そうした人たちの存在が、働きやすさにもつながっています。たとえば、あまり利益にならない案件でも、10人ほどのメンバーが集まり、2時間近く真剣にディスカッションしている。損得ではなく、「良いものをつくりたい」という想いで動いている姿勢が本当に好きなんです。
結局、仕事において一番大事なのは「誰と働くか」だと私は思っています。たとえ給料が高くても、ネームバリューがあっても、死ぬ間際に「この会社で働けてよかった」と心から思えなければ、意味がありません。それよりも、信頼できる仲間たちに惜しまれながら人生を終えられることのほうが、私にとってはずっと幸せです。
──外資系コンサル企業から戻ってきた理由も、そこにあったのですか?
心から信頼できる仲間たちと、一緒に働きたいと思っていたからです。外資系コンサルタント企業に転職したのは、お金が理由でした。双子の娘を私立幼稚園に通わせる費用が足りなくて。当時の社長に「出稼ぎや留学のような感覚で行かせてください」とお願いして、3年後に戻る約束をして転職しました。実際、転職してから、より一層信頼できる仲間の大切さを感じました。ちなみに、ASAKOに復帰する時は3ヵ月ほど無職だったので、自分の貯金から「給料」を振り込んで働いているふりをしたこともありました(笑)。
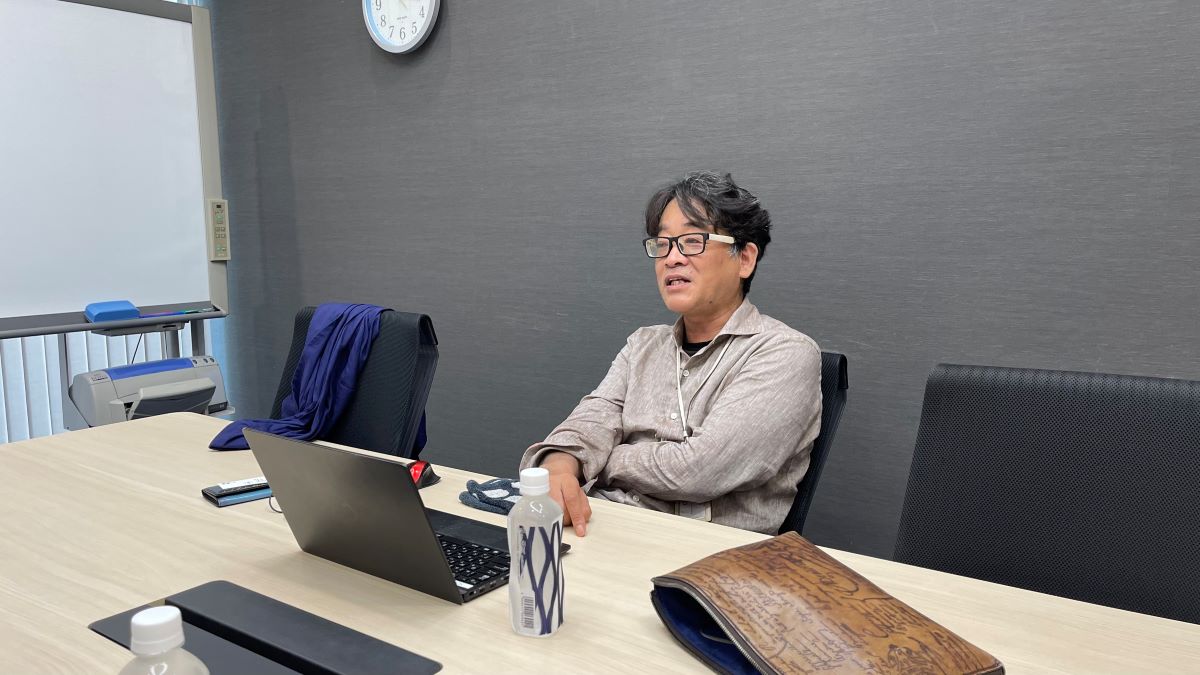
(羽田さん写真) 私自身も20代の頃から将来を見据えていました。ビジネススクールに通ってMBAを取得すること、いつかコンサルティング会社に行くこと、そして本を出すことも決めていました。
5 誰でも「本質をつかむ力」は育てられる
20代からの積み重ねが、今の羽田さんをつくり上げてきたことがよくわかりました。では、それは私たちにもできることなのでしょうか。最後に、「本質をつかむ力」をこれから身につけていこうとする私たちに向けたアドバイスをもらいました。
本質を見抜く力は、特別な人にだけ備わった能力ではありません。多くの人がKPIや売上といった目に見える情報だけで判断しがちですが、もう一歩踏み込んで、背景や因果関係まで見ようとする習慣を持てば、誰にでも身につけられます。もちろん簡単ではありません。数字で判断するほうが楽ですし、背景を考えるには手間がかかります。でも、そのひと手間が、あとで大きな差になるのです。
私は、意識的に因果関係をストックするようにしています。「こういう時にはこうなる」といった知見を、過去の仕事から少しずつ引き出しに蓄えておく。そうしておけば、作業に入る前に考えることができ、実際の行動もスムーズになります。20代の頃から、「一つひとつの仕事を絶対に消費しない」と決めていました。仕事から学びを引き出す積み重ねが、今の自分をつくっています。
──最後に読者へのメッセージをお願いします。
本質をつかめるようになると、人生は格段に楽になります。枝葉に惑わされずに済むからです。仕事でも、本当に大事なことがわかれば、それ以外の部分は手を抜いてもよい領域として割り切れます。精神的にも、業務のスピード的にも、大きく変わってきます。
最終的にキャリアで勝てるのは、やはり「本質を見抜いて、行動に移せる人」だと私は思っています。もちろん、多くの企業では人事評価が1年単位で行われ、その枠組みの中で「今年の評価をどう得るか」が最優先になりがちです。でも私は、その枠に縛られるべきではないと考えています。むしろ、「10年後、自分はどうありたいか」を考えることの方が、ずっと価値がある。社会に対して提供できる価値が高まっていけば、評価は自然と広がり、会社の枠にとどまらなくなります。
だからこそ、読者の皆さんに伝えたいのは、「枝葉の情報にとらわれず、一度立ち止まって背景を考える習慣を持ってほしい」ということです。反射的に動かず、因果関係を意識して思考を重ねる。それを続けていくだけで、きっと見える景色が変わってくるはずです。
本質をつかむ力とBrand PRISM™へ
「本質をつかむ力」は企業やブランドの“存在価値”——つまり、その組織が社会の中でどんな意義を持ち、どんな未来をつくりたいのか——を深く理解し、社内外に共感を広げていくための原動力です。
朝日広告社が提供するBrand PRISM™は、その「本質」を構造的に明らかにし、ブランドの内面と外面を同時に磨き上げることを目的としています。パーパス・ブランドの策定から組織浸透まで、ブランドが強く長く選ばれる存在になるためのフレームワークです。
Brand PRISM™でできること:
- ブランドの「本質(存在価値)」を問い直し、明文化する
- 全社員・ステークホルダーが自分ごととして共感・共鳴できるブランドへと成長させる
- 感情に響くエピソードや共体験をストーリーとして積み重ねる
本質をつかむ力を育み、Brand PRISM™のフレームと掛け合わせたとき、はじめて”単なるテクニックではない、企業ごと・ブランドごとの圧倒的な個性と強さ”が生まれます。これからの「AI時代」「情報濁流時代」に本当に選ばれ続ける存在へ——その第一歩を、私たちと一緒に踏み出してみませんか?
▼ Brand PRISM™の詳細はこちら
https://www.asakonet.co.jp/asunomikata/solution/brandprism/